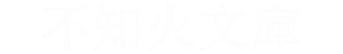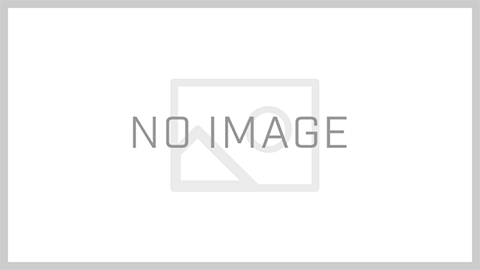第一声は、「お迎えにあがりました」だった。
夕方、チャーハンを炒めていると、左手側に気配を感じた。視線を玄関側に向けると、黒いローブをまとっている何かが立っている。右手には大きな鎌。
チャイムは鳴っていない。鍵はかけていたはずだ。鍋を振る手を止める。油が、ひとつ弾ける。数拍、心臓が、乱れて跳ねた。喉がうまく動かず、声がひっかかる。
「……は?」
そいつがこちらへ向かってきた。あっけにとられている場合ではない。即座に身構える。
「誰やお前」
構えを崩さず、低い声で尋ねる。
「死神です」
──なんの冗談や。
「今日日の死神には足が生えとるんか」
「ええ、その方が何かと便利なので」
視線を足元へ落とす。濃い灰色のスニーカー。泥が、踵にこびりついている。ブランド名までは見えない。
ひと呼吸、間を取る。
「靴、脱げや」
すう、と死神が息を吸う。
「床が汚れるやろ」
「些末なことでしょう。目の前の死に比べれば」
「死に場所が汚いとか嫌やろ、非常識かお前は」
「余裕ですね」
「そうでもないで。結構ビビっとる」
いつの間にか握り込んでいた手をほどく。ひんやりした。汗で湿気っている。
「ご安心を。サクッと刈るだけなので」
「安心できるか。ちょっと待てや」
「駄目です執行時間です」
死神が一歩、踏み出す。
チャーハンが、じゅう、と音を立てる。火はまだついている。
「まだチャーハンの火、止めてへん」
「どのみち食えないんだから問題ないでしょう」
「そういう意味ちゃうわ。今死んだら火事になるやろ。お前、無関係のモンも巻き込むようなやくざな仕事しようっていうんか」
沈黙。死神がわずかに首を傾ける。注意が、一瞬逸れた。
右手を、真横に振り抜く。おたまが死神の側頭を薙ぎ払う。
――ゴンッ。
死神がよろけた。生身の人間のように、こめかみを押さえている。
「なんや、当たるんか」
よろよろして、片膝を床につけている。随分人間くさい動きだ。
顔を見る。鼻がある。骨もある。痛覚も、あるらしい。
「ほなちょうどええわ。飯前の運動に付き合えや」
おたまを握り直す。それと同時に、地を蹴った。
まずは、脛。鞭のように打ち込む。鈍い音。踏ん張る気配がぐらつく。すぐさま回し蹴りで死神の手を薙ぐ。大鎌が手から落ちる。
「ちょ、あ、やば──」
奴が呻き、バランスを崩した。
「死神がやばい言うなや。やばいんはこっちの方やろが」
脇腹に蹴りを叩き込む。鈍い音が響く。
首根っこを掴んで、床に叩きつける。ローブがふわりと揺れた。
死神は、潰れた芋虫のように、じっとしている。
床に転がっている大鎌を回収し、一息つく。
右手を見ると、持っていたおたまが、少しだけ曲がっていた。
鍋の中のチャーハンは焦げかけている。ガスを止め、換気扇のスイッチに手を伸ばす。視界の隅に、黒い塊が転がっている。沈んだまま、微動だにしない。だが、確証はない。コンロ脇の引き出しを開け、三本のナイフを抜き取る。立ったまま、数秒。耳を澄ませる。微かに、布の擦れる音。ローブの下が、もぞ、と動いた。
「……ッ」
反射で手首が走る。ナイフが、空気を裂いて飛ぶ。狙いは外した。ローブの真横、壁際。次は急所を狙える、とわかる角度で突き刺さった。
「動くな。おかわりはいらんやろ」
死神が、ふらふらと上体を起こした。動作は鈍い。足元もふらついている。
「……ひどいやつだ。こんなやつには会ったことがない」
「周りが優しすぎただけとちゃうか。あと、よう考えたら、お前、不法侵入と傷害致死未遂やんけ」
沈黙。
「……確かに……」
「とりあえずしょっ引くわ。手ぇ出せや」
死神は黙ったまま、視線だけをこちらに寄せていた。
「どうするつもりなんですか」
一歩踏み込む。無言で鳩尾へ拳を打ち込む。死神が、再度膝をついた。
「手ぇ出せ言うとんねん。話聞いてへんのか」
死神は、咳き込んだまま、片手を上げかけて止めた。ふらつきながら、言葉を搾り出す。
「……な、殴るのは、通告後にしてください……それと、一応、死神なんで……標的以外には、認識されない仕様ですが、大丈夫ですか?」
声が一層細くなった。
「知らんわ。ええからさっさとせえ」
死神は小さく頷く。諦めたのか、指先を素直に前へ出した。そのまま、手錠を死神の手首に掛ける。カチリ、と音が鳴った。
「とりあえず手錠はしとく。あと、通告については──」
少し間を置いて、目だけで死神を見る。
「次から気ぃつけるわ」
「やっぱり次もあるんですね……」
死神が腹を押さえながら、よろよろと立ち上がる。
「お前次第や。まあええ、部屋上がれ。事情聴取や」
「……はい」
壁に手をつき、足を引きずりながら部屋に向かう。
「靴は脱げ。じゃないともう一発入れる」
死神がぴたりと動きを止める。そして、踵同士を重ね合わせ、ぎこちない動作でスニーカーを脱いだ。
そして、部屋に上がり、死神は正座をした。
――死神って、正座できるんやな。
「お前、チャーハン食うたことあるか」
死神は押し黙る。
「一回、食ってみろ」
「しかし……我々は、そういう生理的行為を必要としない存在で……」
「必要かどうかの問題やない。ええから食えや」
返事はない。チャーハンからは湯気が静かに上がっている。
しばらくの沈黙のあと、死神の手が、そっとレンゲを掴んだ。手錠は、ついたままだ。
米を掬い、運ぶ。さらに湯気が立つ。口元がわずかに動く。ひと口、また一口。しばらく、レンゲは止まらなかった。
「で、そろそろ本題やけど。お前、ほんまは何者やねん」
「……え、と。さっきも言いましたが、一応、本当に死神なんです」
「一応、て何やねん」
手元のおたまを見た。少し凹んでいる。死神は、それを避けるように目を逸らした。
「ていうか、物理攻撃効くんやな」
「はい……まあ」
死神はバツが悪そうに目を合わせてこない。
「それ、今回みたいに標的に暴れられたらめっちゃ大変ちゃうん?」
「はい。それが原因で現場を離れることも、あります」
「ヘタレかよ」
死神が肩を落とす。
「……死神にも裁量がありますから。魂刈る前に拳で刈られたら、洒落にならないですし」
「やっぱヘタレか」
肩を落としたまま、死神はうなだれた。視線を落とし、レンゲを置く。
「仕方ないじゃないですか。実際、病院送りになったり再起不能になったりすることだってあるんですから」
「そんな目に遭ったらトラウマでスランプになりそうやな」
「ありますよ、実際。それで辞めていくものも多いです。刈れない魂、刈れない環境、厳しいノルマ、激しい抵抗。理由なんていくらでもあります」
「死神も大変なんやな」
「はい。それに魂なんて本当は刈るもんじゃないんです。でも、そうするしかない命もあるんです」
俺は、レンゲを止めた。死神がこちらを見ている。
「人間は、終わるタイミングを見失うことが多すぎるんです。痛みだけが残って、意思も記憶も崩れて。それでも鼓動だけは止まらない」
二人とも黙り込む。
――終わるタイミング、か。
「きちんと終わらせる。それがお前らの仕事か」
「はい。現状確認と案内。必要なら、終わらせるんです」
しばらく沈黙が続いた。
「そういうのも大事なんやろな。まあ、お前は今んとこ俺にぶっ飛ばされてチャーハン食わされてるだけやけどな」
死神が肩をすくめる。
「スランプです」
「言い訳、下手か」
レンゲを置く。
「つーか待てや」
「なんですか」
「お前がここに来るってことは、俺の命も、終わるタイミング見失ってるっつーんか」
死神の動きが止まる。顔を伏せたまま、返事がない。
――ゴン!
げんこつ。
「通告……」
「ああ、忘れてたわ」
「……本来なら、私に手を出した時点で、死神中隊派遣事案です」
「は?」
「私、階級で言うと第三位。現場指導官クラスです」
「うち来るなや、そんなやつ」
「私も来たくはなかったです。でも、リストに名前が残っていた」
俺は聞き返した。
「俺ってそんなヤバい案件なん」
「“刈り残し”リストに載ってました。過去、二回出動履歴あり。どっちもあっけなく返り討ち」
「知らんぞ、そんなん」
しばらくの間、互いに沈黙した。思い出せることは、やはりなかった。
「で、今回のエリート様はどうやったん?」
「ボコボコにされて、手錠かけられました」
「チャーハン、忘れてへんか?」
死神が、かすかに笑った。乾いた音だった。
「おかわりならあるで。皿洗いするなら、やけどな」
「乗りましょう」
間髪入れずの返答。
「ちょろすぎやろ、お前」
死神が、また笑う。
「それにしても……あなたはずいぶん長いこと生き残っていますね」
「いや俺も知らんかったんやけどな。今日の今日まで」
「こっちは記録でしか見てないから、“あ、まだ削除されてないんだ”って感じでした」
「パソコンのゴミ箱にあるデータみたいな言い方すんなや」
食事を終えると、死神は食器を重ね始めた。こちらを一瞥し、口を開く。
「洗いますね」
「おう。頼むわ」
台所に立つ背中越しに、水音が響く。しばらくすると、水音が止まった。洗い物を終えて、皿を布巾で拭き始めている。
「私、本当はもうあまりやる気がないんです」
ぽつりと声を落とす。
「エリートなんやろ、お前。それでも、か?」
「それでも、です」
皿を拭く手は止まらない。死神は続ける。
「やる気ないんなら辞めたらええんちゃうか。俺だってどうせならやる気あるやつに刈られる方がましやからな」
「辞める、ですか」
「難しいことなんか?」
死神の手の動きが止まる。微かな静寂。
「わかりません。考えないようにしてたかもしれません」
「なら今日の収穫に、この発見も追加やな」
死神から笑い声が漏れる。
「そうですね。あと、やる気ですけど、あなたの場合はやる気の有無に関係なく刈れないと思います」
「そりゃどうも。安心したわ」
死神は、何度も同じところに布巾を滑らせている。ふと、こちらを見ずに言った。
「私も、感謝されるような仕事をしたいです。人がそうしているように」
「……うまい言い回しやな。どこで覚えたんや?」
死神が一拍、固まる。隙を逃さず、問いを重ねる。
「誰の、真似や?」
布巾を持つ手が、止まる。
「……誰の、ってわけじゃ。まあ、昔、そういうふうに言ってた人がいまして」
「……へえ」
「あと、うまい飯食って、皿洗って、たまに笑って……そういう生活が、いいなと」
今度は、こちらが目線を逸らした。
「昔、俺も似たようなこと、言うてたかもしれんな」
「……」
死神が反応しないのを見て、言葉を足す。
「いや、言われたんかもしれん。“そういうのが一番、まっとうや”って」
「……そういう人、いたんですね」
「まあな。まっとうで、ちゃんとしてて……真似はできんかったけど」
沈黙が落ちる。
「お前、人間みたいやな」
死神は首を少しだけ傾けた。外からの風が、一瞬カーテンを揺らした。
「……そう、ですね」
死神が食器を片づけ終え、こちらへ向き直る。
「洗い物、終わりました」
「おう。一通り聞きたいことは聞けたし、今回は見逃したる。もう帰ってええで」
「それでは――」
死神が口を開きかけて、少し間を置く。
「チャーハン、ごちそうさまでした。おいしかったです」
「おう。あと、“刈れませんでした。あいつは放っておいた方がいい”、って報告書にでも書いといてくれ」
死神は何も返さず、軽く頭を下げた。それきり何も言わず、扉を開けて出ていった。
翌朝。玄関で靴を履いていると、扉の向こうから声がした。
「お迎えにあがりました」
ドアスコープをのぞき込む。こちらに顔を突き出している。
――やっぱり、こいつか。
「……お前、帰ったんちゃうんか」
死神が肩をすくめ、両手を広げる。
「ええ、昨日は帰りました。これから毎日、お迎えにあがりますよ」
ため息が出た。足を踏みしめ、息を大きく吸い込む。そして、勢いよく扉を蹴り開けた。鈍い音とともに、ぐえっ、という妙な声が響く。死神は玄関先で仰向けにひっくり返り、顔を押さえて呻いている。
鍵をかけ、死神を跨いで声を掛ける。
「俺、今から仕事やねん。もう行くで」
背中から情けない声が聞こえたが、無視してそのまま歩き出す。
――餌付け、せん方がよかったかもな……。