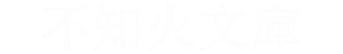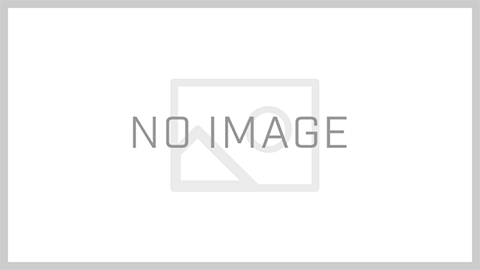外出前、玄関のドアスコープを覗いた。ため息が漏れる。
――今日もか。
玄関前に黒いローブ。扉を開ける。
「お迎えにあがりました」
今日も、いつも通りの丁寧な挨拶。ここ数日、死神は決まって毎朝やって来ている。
「またお前か。今から仕事や、帰れ」
感情を込めず淡々と告げる。
「失礼しました。では」
死神は顔色を変えずそう返し、簡単に引き下がる。毎回同じだ。落ち込んでいる様子もなく、こちらとは別の方向へ去っていく。
他におかしなことは、特に起きない。今日も同じだ。だが、ずっとひっかかっている。何を狙っての行動なのか、全くわからない。
――つけてみるか。
足を止め、踵を返す。
死神は十字路を幾つかまっすぐ進んだ後、近所の公園の方へ入り、ベンチの端に腰掛けた。そこで、たまに背筋を伸ばしたり、行き交うものたちを眺めたりしてはいるが、特に何をするでもないまま数十分が過ぎていった。
翌日も、そのまた翌日も、後をつけた。しかし、特に様子は変わらなかった。
ある非番の朝、目が覚めると部屋の外からざあざあという音がした。空気が微かに湿っている。布団から出ず、そのまま読みかけの本を手に取る。読み進めているうちに、時刻は正午を過ぎかけていた。窓の外に目をやる。いつの間にか、小降りになっている。
布団から抜け出し、手早く身支度を整え、部屋を出た。そのまま公園の、例のベンチへ向かう。ベンチの端には黒いローブが腰掛けていた。ずぶ濡れになっている。膝の上で手を重ね、ぼんやりと空を眺めている。ローブの裾が濡れて重そうだが、気にしている様子はない。
少し離れた場所で、小さな子どもが何かを落とした。連れの母親らしき人も本人も気付いていない。死神はさっと立ち上がり、落とし物を拾い上げた。そのまま後を追い、遠慮がちに子どものカバンの脇へ滑り込ませる。声はかけない。
ベンチに戻ると、今度は周囲のゴミを片付け始めた。淡々と続けていたが、横顔の口角が少し上がっているように見えた。
その姿をしばらく眺めていたが、気付かれないよう背を向け、公園を後にした。
その夜、雨足はまた激しくなった。カーテンの隙間から外を覗く。ここからでは、あのベンチは見えない。まだ、あそこにいるのだろうか。
翌朝になっても雨は降っていた。玄関へ行き、ドアスコープを覗くと、いつも通り黒いローブが立っている。扉を開けると、変わらぬ調子で挨拶してくる。
「懲りへんな、お前。何がしたいんや」
「刈りどきを観察しているんですよ。あなたのね」
――どこまで本気なんや、こいつ。
「ところで、今日もお仕事ですか?」
「いや、今日は非番や。でも、いちいち相手にはならへんで」
死神は小さく息を吐いた。
「はい、わかりました。では」
そのままドアを閉めかけると、「ハックション」と大きなくしゃみが聞こえた。
ドアを開け直すと、死神が身を縮めている。しばらく沈黙が続く。
「……死神って、風邪ひくんか」
死神が首を傾げる。
「仕様上はひかないはずなんですが……」
――仕様ってなんやねん。
死神のローブの裾からは、水滴が滴り落ちている。またくしゃみ。今度は小さく二回。
「はよ帰れ。風邪拗らせてもしらんで」
――帰るっつってもあの公園か……
はっと気が付く。これは、どうでもいいことだ。二の句を継がず、出かけた言葉を飲み込んだ。
「ちょっとそこで待っとけ」
部屋に戻り、使い捨てのタオルを持ち出して死神に差し出す。死神は一瞬きょとんとした。が、小さく頷き、それを受け取った。
「……ありがとうございます」
タオルで身体を拭きながら、死神がぎこちなく頭を下げる。
「なあ、お前の目当ては何なんや。俺の命を狙ってる言うとるけど、やってることは毎朝ここに来るだけや。しかも、すぐ帰るし、何の危害も加えへん」
死神は黙ったまま頭を拭いている。そして、いつものように肩をすくめた。
「決まりですから。仕事です」
本心は分からない。死神を真正面から見据え、わざと、目を合わせる。
「それだけか?」
死神は手元のタオルに目を逸らし、静かに口を開く。
「ええ」
声の調子は変わらない。手は、タオルを畳んでいる。
「お前、なんか隠してるやろ」
死神は顔を上げずに応えた。
「隠し事なんて誰にでもあるものですよ」
やはり調子は変わらない。
「はぐらかすな。何か隠しとるやろ」
「あなた、しぶといですね。昔から――」
死神が一瞬口をつぐむ。
「昔から、そんな感じなんですか」
死神の口角が、微かに上がる。微笑んでいる。
「目当て、他にもありますよ。あなたの家に来ることが、なんとなく、毎日の楽しみになってきてます」
死神は、そう言って頬をかいた。また、ため息が漏れる。
「死神の役割がそれでええんか」
死神は答えない。タオルを握ったまま、手元を見つめている。
「ご心配ありがとうございます。でも、大丈夫です。あなたは、簡単には刈れなそうなので、楽しみながら気長にやるくらいがちょうどいいんです」
死神は立ち上がり、丁寧に畳んだタオルをこちらに返した。玄関に向かいながら、ぽつりと言った。
「無理は、程々にしてくださいね」
――皮肉か?
「死神の忠告としては、なかなかのミスマッチやな」
今日も“お迎え”がやって来て、そして行使されずに終わった。玄関の扉が閉まっていく。口を突いて言葉が出た。
「待てや。飯、食っていけ」
死神が立ち止まり、勢いよく振り返った。頬が緩んでいる。
「いいんですか。ぜひ」
声が弾んでいる。ええで、と軽く頷いて返すと、死神が嬉しそうに言葉を継いだ。
「こないだのアレ、おいしかったんですよー。あなたの料理、他にも食べたいです」
他人行儀なくせに、なぜか妙にノリが軽い。素直、というべきか。それとも、好奇心旺盛なのか。思わず鼻からため息が漏れる。
――食い意地かもしれんな。
「やっぱりちょろいっつーか、調子のええやつやな、お前」
小さくぼやいた。聞いているのかいないのか、死神は玄関で靴を脱ぎ始めた。
「あの……すみません」
死神がおずおずと声を出す。
「私……ずぶ濡れなので。部屋を汚してしまいそうです。やっぱり今日は、出直した方が――」
見ると、死神は玄関の框で濡れたローブの裾をつまんでいた。さっきまでの明るい様子が一転し、遠慮がちな声になっている。気まずいのか、こちらに目を合わせない。
――いざというときほど遠慮するんかな、こいつ。
「わかっとる。濡れとるもんはしゃあない。玄関先で絞れるだけ絞って上がったらええ」
死神は小さく頷き、ありがとうございます、と呟いた。そして、ローブの水を切り部屋に上がった。
「今作ってたとこやから、ちょっと待っとけ」
冷蔵庫を開けて、残り物の野菜や卵をかき集める。
――飯を食わせれば、何か情報を話すかもしれんしな。
死神はローブの裾をきちんとまとめて膝の上に乗せ、正座している。観察でもしているかのように、視線がこちらの動きを追いかける。
「なあ、死神って普段は何食うんや? 前来たときの感じやと、人間が食うもんは別に食わんでもええみたいやけど」
炒めものを返しながら尋ねると、死神はすぐに答えた。
「食べなくても問題はないです。ただ、こっちに長くいると、“お腹が空く”という感覚が理解できるようになってしまうようです。しかも、人間のご飯はすごく美味しいので、毎日でも食べたくなっちゃいます」
「なんやそれ。食い意地張っとるだけちゃうんか」
「そうかもしれませんねえ」
死神はあっけらかんと笑っている。
たわいもない話をしているうちに、朝食の支度が整った。
「ほれ、できたぞ。即席の野菜炒め定食や」
納豆の小鉢を置き、最後に味噌汁を手渡すと、簡素な定食がひとまず揃った。ごはん、野菜炒め、納豆、味噌汁。どれもありあわせだが、それなりの形にはなった。
死神は両手でそっと味噌汁の椀を受け取り、湯気をゆっくりと吸い込んだ。しばらくじっとしていたが、いただきます、と小さく呟き、箸に手を伸ばした。炒め物からひと口食べる。
「やっぱり人間の食事って、いいですね」
嬉しそうに微笑んでいる死神を見て、ふと疑問が浮かんだ。
「……お前って、元は人間なん?」
箸が止まり、死神はわずかに目を瞬かせた。反応は薄いが、すぐには答えてこない。
「そうかもしれません」
少し言い淀み、死神は味噌汁に視線を落とした。湯気を見つめるように、言葉を選びながら続ける。
「この姿でいる以上、“人間だったことがあるかもしれない”と考えるのは自然なんでしょうね。でも、私にも分からないんです。それに、元、なんかなくて最初から死神だった、ということもあるかもしれませんし」
ただ、と死神は続ける。
「こうやって誰かと一緒にご飯を食べていると、なんだか懐かしい気持ちにはなります。だからきっと、どこかで……そういう時間を過ごしたことがあるのかもしれません」
最後だけ、死神の声が細くなった。俺は何も言わず、ご飯を口に運んだ。
その後は、箸の音だけが部屋に響いた。互いに黙って食べ進めるが、不思議と気詰まりではなかった。味噌汁を飲み干した後、死神は箸を置いた。そして、椀をきちんと揃え直し、膝の上に両手を置いて頭を下げた。
「ごちそうさまでした。とても美味しかったです」
食後、死神はきれいに食器を洗い、布巾で拭いてから台所に戻した。死神がこちらに声をかける。
「では、そろそろ失礼します」
そう言った後、小さく鼻をすすった。
「お前、寝泊まりするところあるんか?」
聞かなくても察しはついている。死神は少し間を置いたあと、飄々とした声で言った。
「ありますよ。なかなかいいところが」
「それ、この近くの公園のことか?」
「ええ」
一瞬、間が空く。隠す気もないようだ。
「そんなとこで寝とるから風邪引くんや」
「そうかもしれません。でも、結構楽しんでいますよ」
キャンプでも楽しんでいるような口ぶりで笑っている。不自由を愚痴るでも嘆くでもない。
「まあええ、もうちょい休んでいけ」
そう言うと、死神は小さく口ごもり、両手を小さく振った。
「それは、ちょっと……いくらなんでも申し訳ないですし」
「人の家で気軽にたらふく食うやつの言葉とは思えんな。ええから上がれ。まだ雨も降っとるやろ」
――この機会に、できるだけ自分の状況やこいつのことを掴まなあかん。
「……忘れていませんか。私はあなたの命を刈ろうとしているんですよ」
にやり、とわざと口角を上げる。
「狙いたきゃ狙ってええぞ。思い通りにはさせんけどな」
死神はあきれたようにかぶりを振った。口元が微かに緩んでいる
「……お言葉に甘えて、少しだけ」
小さく息をつき、ローブの裾を持ち上げ、再び部屋に戻ってきた。
「あなた、不思議な人ですね」
「はじめて言われたわ。そんなこと」
すっとぼけると、死神はわずかに目を細めた。笑っているのかどうか、よくわからない。ただ、敵意は感じない。
――少なくとも、”まだ”