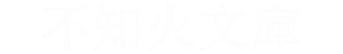彼と知り合ったのは、行きつけの喫茶店だ。数年前、カウンター越しに店主と他愛のない話をしていたとき、彼もその輪に加わってきた。ごく自然に、滑り込むように輪に馴染んだ。以来、顔を合わせればよく語り合うようになった。
ある日、学生の頃自転車を盗まれた、という話をした。彼はにやりと笑って口を開いた
「ああ、俺もあるわ。小倉でな」
「小倉って、北九州の?」
「そうそう。乗っとるときに盗られてな」
ひゅ、っと変な息が漏れる。
「何それ。信号待ちとかで降りとったんちゃうん」
「いや、漕いどった」
「は?」
変な笑いがこみ上げた。声が大きかったのか、少し離れた席の常連がこちらを振り返った。
「いやいや、無理やろ。漕いでる最中とか」
「あるんよ、それが。修羅の国やけん」
「説明、雑過ぎやろ。あり得へんわ」
「あり得たねん」
彼はなぜか誇らしげな顔をしている。訝しむ顔をしていると、彼は静かに語り始めた。
「俺、チャリで高校に通ってたんやけど」
一息つき、そのまま続ける。
「学校からの帰りに、いつも通る街中をゆるゆる走っとったねん。そしたら、横から急に男が出てきてな」
無言で頷き、続きを促す。
「そしたらそいつ、急にチャリのハンドルを掴んできたねん。で、無理やりサドルから押し出された」
「は?」
「『お前、何しよっと!』って言う間もなかったわ。地面に転げ落ちてな。で、そのまま、チャリごと逃げられてもうた」
「え、怖。もうそれ、強盗やん」
「チャリ版カージャックやな。F1のピットイン並みの早業やったで」
「怪我は?」
「かすり傷で済んだわ。ま、運が良かったんやろな」
──どこがやねん。でも、まあ……そうかもな。
カフェラテを啜った。ミルクの甘さが、少しだけ舌に残った。
「……で、警察行ったん?」
「行った行った。交番で言うたら、『またか』って言われた」
「またか……?」
「『よくあるんですよ』って」
「よくあるんかよ」
店の奥から、豆を挽く音が静かに響いている。
「まあ、修羅の国やけん」
──真顔で言うような話かよ。
思わず口の端が緩む。
「全部それで押し切んな」
彼がカップを軽く傾ける。
「で、自転車は見つかったん?」
「いや」
「そうか。災難やったな」
「まあな。まだどっかで使われとるんかなあ、俺のチャリ」
そう言って、彼は笑った。私は答えず、空になったカップをぼうっと眺めていた。
「さて、そろそろ行くわ。またな」
「おう」
彼はカウンターに代金を置き、静かに席を立った。扉が開いて、風が入る。窓の外を眺めていると、彼が自転車で去っていくのが見えた。