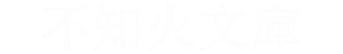【1】
不本意な命名をされてから、数日が過ぎた。この家での暮らしは、思いのほか静かで、快適だ。ある薄曇りの朝、玄関から声がした。
「ちょっと買い出し行ってくるわ」
顔をのぞかせて返事をする。
「わかりました。じゃあ、私は掃除でもしておきます」
「おう、頼むわ」
扉が閉まり、鍵のかかる音がした。部屋は、いっそう静かになった。
居間のソファに腰を下ろし、深々と息を吐く。束の間のひとり時間だ。数日前、彼が押し入れから引きずり出してきたエプロンを身につける。紺一色で無地の、素朴なデニム地だ。
チューナとアンプの電源のスイッチを入れ、ラジオをつける。ピアノの音色が耳に届く。
──ハニーサックル・ローズ、か。ビル・エヴァンスの。
演奏を聴きながら洗濯機の前へ向かい、洗濯物を放り込む。洗剤と柔軟剤を入れ、蓋を閉める。それから、ボタンを押すと、洗濯機が唸り始めた。
唸る洗濯機を背に、掃除機を取り出す。フローリングを一通りかけてから、ソファの下に溜まった細かな埃を吸い込んでいく。
ひと通り終えると、台所に向かう。流しに残っていた湯呑と茶碗を手に取り、水で濡らす。指先で汚れの縁をなぞりながら、静かに洗っていく。
「生きてる人間がやることのはずなんですけどねなんだけどな、これ」
水を止め、布巾で手を拭く。窓の外から、子どもの笑い声が聞こえてきた。近所の子たちだろう。子どもたちの賑やかな声に耳をそばだてる。
──たしか前にも。
はっ、と我に返る。口元が、なぜか緩んでいた。どうも、調子が狂う。一つ大きな息をつき、布巾で居間のテーブルを拭いていく。それから、テレビのリモコン、置きっぱなしの新聞などをまとめる。他のものも、あるべきところへ整頓する。不要なものはごみ箱に入れた。
人の営みの繰り返していると、自分が人であるかのように思えてくる。懐かしさを覚えることさえある。長居する現場では、大体こうなる。が、今回はそれが顕著だ。
「やれやれ。人間の営みの侵食力、恐るべし」
上を見て、ため息をつく。天井には、照明が静かにぶら下がっている。視線を落とすと、壁の額縁が目に入った。縁に触れると、ひんやりとしていた。
「夜のカフェテラス……。活気と、孤独。あの人あいつらしい、のかも」
しばらく、ぼうっと絵を見つめた。姿勢を直そうと足の位置を変える。その瞬間、鋭い痛みが足に走った。
「……っ」
慌てて足を浮かせる。
──画鋲。
親指付け根に刺さっている。掃除機をかけたとき、見落としたか。拾い上げ、机の隅に置いた。天井を見上げる。照明が、微かに揺れていた。ゆっくりとソファに腰掛ける。彼は、もうじき戻ってくるだろう。気づけばまた、口元が少し緩んでいた。
程なくして、鍵が開く音がした。玄関へ向かい、声を掛ける。
「おかえりなさいませ、ご主人様」
彼は眉をわずかにしかめ、開口一番言った。
「二度とそれ言うな。気持ち悪いわ」
「居候の身で提供できるサービスの一環かな、と思ったのですが」
呆れたように片眉を下げ、彼は、短くため息をついた。
「それやったら、肩でも揉んでくれ」
「隙だらけになりますね。刈り取りますよ、命」
「ほんまにやるやつは警告せえへんわ。チャンスが来たら、黙って殺るねん」
表情を和らげ、彼がふっと笑う。こちらもつられる。こういうやり取りが、挨拶代わりになってきている。
そのままキッチンに向かい、買い物袋の中身を順に取り出す。じゃがいも、たまねぎ、豚肉、豆腐、卵、牛乳。別の袋には、みりんと料理酒、切れかけていた醤油の詰め替えもある。彼は、決まった場所にそれらを収めていく。
その後、彼は冷蔵庫の上段から調理器具を取り出した。何を作るかは言わない。やがて、彼はまな板の上で野菜を刻み始めた。その響きは、なぜかいつも音楽的だ。こちらの呼吸まで整っていく気がした。
「……ひとつ伺ってもよいですか?」
「なんや」
彼は手元に目を向けたままだ。
「どうして料理をご自分でなさるんです?」
「俺以外に誰が作るねん」
「選択肢としては私も可能性に含まれるかと」
「毒盛られたらたまらんやろが」
「なるほど。たしかに」
素直にうなずく。また少し間を置き続ける。
「ご安心ください。そんな陰湿な手段は取りませんので。やるときは正々堂々いただきますよ」
「できるか、アホ」
だが、口元は笑っている。しばらくして、まな板の音が止まった。フライパンに油を引き、火にかけ、振るう。油が弾け、にんにくの香りが立ちのぼる。
その動きを目で追う。火の強さ、鍋の振り方、食材の大きさ、鍋に入れるタイミング。全てに「加減」という概念が絡んでいる。
「なんや、料理番組でも見てる気分か?」
フライパンを返しながら、彼が言った。
「傍できちんと見てみると、あなたの生活、意外と複雑なんですね。あと、丁寧です」
「そうか?」
彼が鍋に野菜を放り込む。火加減を絞りながら、調味料に手を伸ばす。
「ええ、私のような者よりは。刈るだけの存在にとって、繊細な加減はほぼ無縁なので」
へえ、と彼が返す。
「ところで」
「なんでしょう」
「冷蔵庫から醤油取ってくれ」
「醤油。ああ、あの……死を早める塩分の化身ですね」
彼が呆れたように笑った。ツボだったのだろうか。
「お前、醤油になんか恨みでもあんのか」
声の端に、まだ笑いが残っている。
「“殺すための道具”には敏感なだけです」
「いや、もうええわ。はよ取ってくれ」
立ち上がり、冷蔵庫から醤油を取り出す。濃口だ。
「こちらですね」
手渡す。
「おう、ありがと」
そう言うと、彼は匙を使わず、直接フライパンに注ぎ込んだ。少しして、小皿に煮汁を垂らし、指先で持ち上げてひと口。うん、と小さく呟いた。
「さっきの話やけどな、お前は家事全般がかなりうまい。あと、煙草を楽しめる。刈り取りを保留して命を見つめることもしてる。それは、複雑とか丁寧、ってことにはならへんのか」
わからない。だが、そうかもしれない。
「……たしかに、そうかも……」
口の端を微かに上げて、彼が言う。
「せやろ。なかなかおもろいで、お前。嫌いとちゃうわ。ま、油断ならんけどな」
腹の底に何かが沈む。恐怖のような感触だった。だが、それだけではない。なぜか、嫌ではなかった。
──ありがとうございます。
そう言いかけたとき、鍋の中で小さな破裂音がした。
「おっと」
彼は手早く火を止め、蓋をした。
「飯できたで、運んでくれ」
頷き、立ち上がって食事を運ぶ。豚肉の甘辛煮に、炒め野菜。質素だが、栄養バランスはしっかり考えられている。
配膳を終えた後、テーブルに着いた。箸を取りかけて、手が止まる。
──侵食されている。ここ数日は特に。自分が誰で、何なのか。存在する意義と理由。それらが剥ぎ取られていく。あるいは……。
「なんや、食わへんのか?」
言い淀む。目の前のものは、本来、私には必要のないものばかり。“死”しか扱わない私が、“生”の営みを模倣している。
「……なんか、不似合いですね」
「何がや」
「この食卓の色、形、温度。全てが死からほど遠く、“生”の象徴に見えます。私だけですよ、”死”の象徴なのは」
「急にどうしたんや。それに、食材はみんな死んでる。ある意味では”死”の象徴や」
「詭弁ですよ、それは。刈る側から見ると、“生活感”ほど強固な命の証はありません」
彼は甘辛煮を口に運びながら言う。
「まあ、たしかにな。“今日も飯がある”ってだけで、だいぶ生きてる気にはなるな」
「でしょう」
「せやけどな……」
「はい」
「“生活感”で命は守られへん。人なんか、予兆もなしに、あっけなく死ぬ」
「……」
返す言葉がなかった。明確な事実だ。死は突発的に、理不尽に訪れる。“生活感”が、死から慈悲を引き出すことなどない。
互いに黙る。ラジオの音が、やけに響く。
「……過去に何か、あったんですか」
目を少し伏せたまま、低く呟いた。
「……さあな。あったとしても、お前には教えん」
何も言えず、小さく頷いて返した。
「私は、少し混乱しているのかもしれません」
「ほう」
「この数日間、私は“あなたの死”を一度も意識していない。これは、業務的には非常にまずいことです」
「ええんちゃう、休んだら。その方が俺も助かるし」
「私たちに休暇という概念はありません。常時、任務対象を把握し、潜在刈り取り可能性を評価し続けなければいけないんです」
「真面目なことで。つーか、そんなんしながら家事してるんか?」
「理想としては。しかし、できていません」
彼は考えるような様子。そして、ふっと笑った。互いに笑う。その“笑い”には、どこか奇妙な温度があった。
「まあ」
言葉を継ぐように、彼がぽつりとこぼす。
「死神でも、生きてるやつらと同じことくらい、してもええと思わへんか。休むとか、飯食うとか。したいなら、やけど」
返す言葉が見つからず、黙っていると、彼が続けた。
「ええから、とりあえず食え。なかなかうまいぞ」
それには答えず、彼に問う。
「ひとつ、訊いてもいいですか」
「なんや」
「あなたにとって、私ってどういう存在なんですか」
「面倒くさいなお前……死神はかまってちゃんなんか?」
無視して、言葉を続ける。
「人間の基準ではなく、“あなたの中で”の評価で構いません」
彼は箸を止めた。しばらく黙って、天井を眺める。
「家賃払わん上にポンコツやけど、家事だけ有能な変なやつ」
「それは……喜ぶべきなんでしょうか」
「知らん、お前の受け取り方次第やろ」
「私のアイデンティティが狂いそうです……」
彼の表情がかすかに緩んだ。苦笑いのような、呆れたような。
「いい機会やろ。“生”に巻き込まれたんなら、もうちょい“生”の側から物事を捉えたらどうや」
「“生”の側……」
ふ、と口の端が上がる。
──悪くないか、生者の真似事も。
「なんか言うたか?」
「いいえ。いただきます」
湯気の温度を感じる。匂いも、ちゃんとある。美味そうだ。一口、運ぶ。やはりうまい。彼がこちらを見て、声を掛けてきた。
「ところで、家の中、めっちゃきれいにしてくれたな。助かるわ」
思いのほか胸に響く。頬が緩みかけたと、少し遅れて気が付いた。
「こう見えて、勤勉ですから」
「本業以外ではな」
彼がわざとらしく意地の悪い顔をする。
「本業達成のための布石です」
「そんな悠長なことしてたら、達成前に“定着”してまうんとちゃうか?」
「心配には及びません。必ず刈り取りますから」
【2】
食卓には、空の器が並んでいる。箸を置き、器を見下ろす。
「ごちそうさまでした」
小さく頭を下げると、「おう」と言い、彼は軽く頷いた。
食器を重ねて流しへ運び、蛇口をひねる。水の音が響く。汚れを水で軽く落とし、水を張ったたらいに沈めていく。
居間に目を向けると、彼は椅子の背にもたれていた。壁の額縁をぼんやりと眺めている。視線の先には額縁──”夜のカフェテラス”の複製画──がある。やはり、なぜか彼によく似合っている。
居間に戻り、急須に湯を注ぐ。緑茶の香りが立ちのぼった。しばらくした後、湯呑をそっと並べ、ひとつを手渡す。
「お茶、入りましたよ」
「おお、サンキュ。そういや、ええもん買ってきてるで」
ビニール袋の口を開け、そこから包みを取り出した。
「出町ふたばには負けるけどな。これもなかなかやねん」
「出町ふたば?」
「ああ、昔通っとった大学の最寄駅近くにある和菓子屋や。大学んときはしょっちゅうそこの大福を食ったもんや」
言いながら、彼は包みをほどいていく。
「へえ、甘党だったんですか」
「ツレにつきおうてるうちに、そうなってもうた」
柔らかい皮を、ゆっくり裂いて見せる。餡が、覗く。
「どんな方だったんですか」
湯呑を手にしたまま、考え込むように黙り込む。彼はしばらく何も言わなかった。湯気が、ゆらゆらと揺れている。
「……変なやつやったわ。あと、めちゃくちゃに頭がよかった」
そう言って、懐かしむように静かに笑った。
──いい友達、だったんですね。
そう言いかけた、その瞬間。
──ガツン。
衝撃。頭の上に、硬いものがぶつかった。
「……っ……」
──え、と彼が短く漏らす。
視界の端で、何かが跳ねる。額縁だ。遅れて、痛みが鈍く響く。咄嗟に身をすくめ頭を抱えた。
「どないした、大丈夫か」
静かに息をつきながら、背を起こす。
「……はい。問題はありません。少し、驚いただけです」
しゃがみ込み、額縁を拾い上げる。少し歪んでいた。彼は釈然としない表情をして呟く。
「釘、ゆるんでたんかな」
壁を見る。たしかにフックがわずかに傾いている。彼は何も言わない。部屋が、しんとしている。
「こういう形で傷を負うことなど、滅多にないのですが……」
ふいに、天井からカチャリと音がした。反射的に見上げる。シーリングライトのカバーが傾いている。
「あ……」
動いた。が、避けられず、前頭部に衝撃が走る。派手な音を立てて、カバーが床に転がった。
「……っ」
また、頭を抱える。今度のは、さらに痛い。そして彼と、黙って顔を見合わせる。
何かを考えるように、しばらく彼は黙っていた。が、やがてぽつりと呟いた。
「お前、嫌われてるんちゃう?」
「ええ……何にです?」
「幸運の女神、とか」
「……否定できませんね」
「あと、言っとくけど、額縁と照明カバー落ちたん、初めてやからな」
「……そうですか」
頷いてそう言った瞬間、何かが口元めがけて飛んできた。
──大福……?
「……あ、どうも」
塞がれた口で、礼を言う。思っていたより間の抜けた声だった。
「それ、食べさせてくれたんちゃうと思うで」
頷くだけで返事はせず、ゆっくりと咀嚼してから、口を開いた。
「これ、ほんとにおいしいですね」
「せやろ。でも、今それ言うか?」
呆れたようにそう言った。湯呑をそっと置き、もう一つ、大福に手を伸ばす。そして、静かに頬張った。彼はこちらを見ながら、椅子にもたれ直した。
「それにしても、どうなってるんやろな。明らかにお前だけ狙われとるよな」
頷いてから言葉を継ぐ。
「ええ。これ、あなたを守る存在が関係してませんかね」
「あー……」
曖昧な相槌を打ち、彼は目を伏せた。
「今のところ、あなたが近くにいるときしか攻撃されていませんし」
机の上の、画鋲に目をやる。
「そうなんか」
「ええ。歓迎されていないのかもしれませんね。一応、あなたの命を狙う存在なので」
「一応って自分で言うんか。お前、それでええん?」
「休暇中ですので」
「さっきと言うてること変わっとるやないか」
口元がまた緩みそうになったが、応じず、ソファに腰を下ろして言葉を継ぐ。
「あなたを守るため、かもしれませんね」
彼は机の端に腰かけ、腕を組んだまま宙を見ている。時計の秒針が、いつもよりよく響いている。
「……なあ」
「なんでしょう」
彼がこちらに向き直る。
「ほんまに、そうなんかな」
「と、言いますと?」
「額縁もカバーも、たしかにピンポイントでお前に落ちてきてるけど──」
「はい」
「最初の夜よりずっと穏やかやろ」
「たしかに。最初は植木や家電まで飛んできましたからね」
「俺を守りたいってのは、たぶんあるやろな、と思う。でも、それだけとちゃう気がすんねん」
──たしかにそうだ。本当に守ることだけが目的なら、最初の夜のように、もっと明確な意志と力で狙い撃ってくるはずだ。それも、四六時中。
「さっきのは、どう考えても軽すぎる。詰めも甘い」
彼は、小さく目を細める。
「本気、ではないと?」
「たぶんな。本気やったら、少なくとも刃物投げたり、拳銃ぶっ放したりするはずや」
「なぜでしょうね」
「わからん。ただ、俺を守ってるやつの目的は、“俺を守ること”であって、“お前を倒すこと”やないってのは確かやろな」
彼が、こちらに目を向けた。そのまま句を継ぐ。
「そこに──、お前が突然入ってきた。俺の命を刈るために」
「そうですね。最初は明確な拒絶。ですが、それきりでした」
ひと呼吸おいて、言葉を継ぐ。
「なのに、ここにきて攻撃が再開している」
「……なんなんやろな」
彼は額縁を拾い、壁に立てかけた。
【3】
「ぶしつけで申し訳ないのですが、あなたの過去について少し伺ってもよろしいですか。幼少期に遭遇した事故の話です」
言葉が、口を衝いて出た。自分の声がいつもより低いと、話し出してから気が付いた。
「何や、急に」
彼が眉をひそめる。だが、棘は感じない。そのまま続ける。
「あなたを守る存在がどのような存在かを知るためです」
そうすれば、先ほどまでの出来事について何かわかるかもしれない。
一連の出来事は、偶然とは思えない。真っ先に考えられる原因は、彼を守る存在だ。彼はしばらく黙ったまま、壁の方を見ていた。
「……前に言うたやろ。“そいつ”は、事故のあとに現れたって」
「ええ、仰ってました。爆発事故に巻き込まれた、と」
壁に立てかけられた額縁を一瞥し、彼はこちらに目を向けた。彼と目が合う。
「そこまで話してたっけな」
目だけ額縁に向け、目を逸らす。
「まあええわ」
そう呟いた後、彼は大きく息を吐いて、静かに話し始めた。
「正直、よう覚えてへんねん。五歳やったしな」
彼は水をひと口飲み、ソファに浅く腰掛けた。何も言わず続きを待つ。
「事故があった場所は、なんかの施設や。研究所みたいなとこでな。おとんがそこで働いとった。その日はたまたま、おかんと一緒に弁当届けに行ったねん」
彼が、言葉を探すように黙り込んだ。
「で、気がついたら、病院やった。何が原因かは知らんけど、爆発事故があったと後から聞いて知った」
胸の奥が、わずかに重くなる。言葉は、すぐには出てこなかった。
「……ご両親は、その事故で亡くなったんでしたね」
「ああ」
「でも、あなたは助かった」
「まあ、な。半月くらい昏睡状態やったらしいけど」
もう少しで死んでいたという事実が、他人事のように語られた。
「で、気がついたとき、病室の棚にあれがあったんや」
「あれ、とは」
「ぬいぐるみや」
彼は、PCデスクの上棚を指さした。手のひらに収まるほどの、小さなクマのぬいぐるみだ。毛並みはくすみ、右耳は少し潰れていて、リボンはほどけかけている。長いあいだ抱かれていた時間が、そのまま沁みついているかのように見えた。
「元々はおかんのやつやったのをおさがりでもらったねん。ちっさい頃は、寝るときも一緒ってくらい大切にしてた。で、事故んときも手に持ってたんや。一緒に吹っ飛んだはずやのに、気ぃついたら、病室にあった」
彼はぬいぐるみを見つめながら、そう言った。わずかに眉が下がっていた。
「ただ、病院の誰に聞いても、置いた覚えがない、って言うねん」
黙って頷き、続きを待つ。
「その頃からや。何かが俺の傍におる、って思うようになったんは。車に撥ねられても骨折ひとつなかったり、三階から落ちても無傷やったり。一回だけならわかるけど、何回も続くとか、普通あり得へんやろ」
頷いて返す。
「記録上、それらの件はすべて“幸運”で処理されていました」
「調べてたんかよ」
「もちろん。対象者の生存傾向は、任務前にすべて精査しますので」
「うわ、いやらしい死神やな……」
「周到、と言っていただけませんかね」
「ほんまに周到やったら、俺を刈ることなんて、試してみようとも思わんやろ」
彼は、呆れたような表情で苦笑している。そのままクッションを枕にして、ごろんと横になった。
「で、その傍におる奴がたぶん今も俺を守ってる。そいつの狙いも正体も分からへん。でも、そいつのおかげで、俺は無事に生きてこられた」
「……もしかして、ですが」
彼がわずかに眉を上げる。
「自分の命が、自分だけのものではない感覚。そういうの、ありますか」
彼はそれに答えず、ただ黙って天井を見ていた。
しばらくすると、彼はすっと立ち上がり、ぬいぐるみを手にした。
「……ガラとちゃうよな?」
「ガラ?」
「こんなん持っとるタイプちゃうやろ、どう見ても」
苦笑しながら、彼は掌でぬいぐるみを転がしている。
「そうですね。でも、ずっと持ってるんですね」
「まあな」
「このぬいぐるみ見てると、時々よう分からん気持ちになるねん」
黙ったままでいると、彼が口を開いた。
「俺を守るために、誰かがこれに何か残したんかなって」
──そうですね。
言いかけて、口をつぐんだ。
「その“誰か”や“何か”、もしそういうのがあるとしたら、普通は真っ先におかんかおとんやと思うやろ?でも、たぶんちゃうねん。俺はそれが“親”やと感じたこと、一回もないんよ」
そう言うと、彼はテーブルの上にぬいぐるみをそっと置いた。そして、ソファに戻ってあぐらをかき、しばらく目を伏せた。
「研究職でしたよね、ご両親」
「ああ。何を研究しとったかは知らんけど、いつも帰りが遅かった。特に、おとんが」
彼の顔を見る。表情からは感情を読み取れない。
「そのせいかな。俺、おかんのことはそれなりに思い出せるねんけど、おとんのことはあんまり覚えてへんねん。ただ、嬉しそうに難しそうな話をしてきたことと、机に向かって夢中で何かしてた背中だけは、今でも覚えてる」
黙って彼の話を待つ。
「……そんなやつやから、たまに早く帰っても、自分の話ばっかりするねん。おとんは俺のことなんかどうでもええんやろなって、ずっと思ってたわ。けど……」
主人公は首を横に振る。
「ほんまは、ちゃうんやろな。今更確認のしようもないけど」
「……ええ」
それ以上は、何も言えなかった。
テーブルの傍で膝を折り、ぬいぐるみに目を落とす。
「親だったらよかった、と思いますか。ぬいぐるみの中身」
「……分からん。ちっさい頃なら、そう思ったと思う。でも今やったら、申し訳ないと思ってしまいそうや」
気が付くと、深く息を吸っていた。吐きだしながら、彼に目を向ける。
「たぶん、大丈夫です」
ゆっくりと言葉を選びながら告げる。
「あなたが感じている通り。このぬいぐるみに、ご両親がいるわけではなさそうなので」
彼がこちらを見る。わずかに眉をひそめている。
「そういうの、分かるんか」
「まあ、多少は」
彼は何かを考えるように黙り込んだ。
「でも、何かが入ってるんは間違いないんやろ?」
ぬいぐるみに目を落としたまま、答える。
「いえ。これは、住処や止まり木みたいなものです。たぶん」
「住処?」
「あなたを守る存在の、です。家であなたと一緒のときだけ、よくここで休む、みたいな……そんな感じだと思います」
「そいつが何かはわからんのか?」
「そこまでは……」
彼の目が、まっすぐこちらを向く。
「……ほんまか?」
「ええ、すみません」
そう答えると、彼は目を逸らした。何かを考えるような表情のまま、しばらく沈黙が続いた後、彼は静かに口を開いた。
「まあええわ」
そう言われて、私は咳を一つついた。気を取り直すように、話を戻す。
「話を戻しますね」
目配せの後、彼は静かに頷いた。
「私を攻撃しているのは、状況から考えて、おそらくあなたを守る存在だと思います」
「そやろな」
「最初は、排除すべき存在だったはずです。実際、ここに来た日の夜、あなたの命に触れようとすると猛烈な攻撃を受けました。ですが……」
一息つく。
「それ以降、あのような激しい攻撃は一度もありません」
「なんでやろな」
「あなたの命を狙うことにあまり積極的でないから、でしょうかね」
「ま、職務放棄してるもんな」
「失礼な。私はエリィ~トですから、職務放棄などしません。ただの休暇です」
彼は、ふう、と鼻から長い息を吐いた。
「何がエリィ~ト、や。ポンコツのくせに」
彼は肩をすくめ、苦笑まじりにそう言った。
「ですが、ここにきてまた攻撃が始まってはいます。ただ、以前ほど激しくはありません」
つまり、と彼が言を継ぐ。
「排除するほどではないけど、目障りではある。そんなところか」
短く頷く。
「自分を差し置いて、あなたとどんどん仲睦まじくなる私が、目に余る、とか」
彼は呆れたような顔をした。
「別に睦まじくはないやろ」
わざとらしくため息をつき、軽く睨むように彼を見る。
「そういうことは、思っていても黙っておくべきだと思います」
返す口元が、なぜか緩む。彼も同じようだ。
「かもな。つうか、ほんまにやきもちなん?」
「可能性はあり得るかと」
「まじかよ、めんどくさいなあ。お前ら」
彼はあぐらを崩し、背中からごろりと寝転がった。
「ところで、お前って標的以外から攻撃されたらどうするん?」
「場合によります。ただ、今回は逃げるわけにはいきませんね」
ため息をつく。
「居心地のいい住処がかかってるからか?」
「それも、理由の一つです」
一拍置いて、言葉を継ぐ。
「なので、あなたを守っている存在に、きちんと筋を通します」
そう言って、天井を見上げた。照明のフックが、わずかに揺れたような気がした。
「筋を通すって、何の話や」
「私の役目について、です」
ああ、と言い、彼は続ける。
「やめへんのやろ?」
「はい、ですが……あなたがきちんと自分の命を活かし、取り返しがつかない程に道を踏み外さない限り、刈り取り執行は保留する。このことをきちんと言葉にして誓います」
ぴゅう、と口を鳴らし、彼はにやりと笑った。
「それ、死神の規則に、背くんちゃう?」
「今まで通りですよ」
そう嘯くと、せやな、と彼は短く笑った。
第四章
「すみません。つらいことを思い出させましたよね」
「ええよ、別に。どうせ、いつかは誰かに話す気ぃしてたし」
淡々とした声だった。
「それでも、私でよかったのかなと」
「誰でもええってわけちゃう。お前はお前で、ようわからんけど、まあ悪くなかったわ」
そう言って、彼は一瞬にやりとした。
「そう思ってもらえたなら、何よりです」
「ああ、ありがとな」
彼の方を見た。目も、笑っている。
──こういう笑い方も、するんだな。
すっと立ち上がり、居間の中央で足を止める。背筋を伸ばし、ゆっくりと息を吸う。息を整えるたび、空気が少しずつ張り詰める気がした。視線は定めない。何を見るでもない。ただ、”そこにいるはずの存在”へ向けて、深く、静かに頭を下げた。
──姿は見えませんが、この方を守っている方。大変、失礼を致しました。
空気が、わずかに揺れる。視線の端で、彼がわずかに目を伏せた。
──私は、この方の命を刈る存在です。しかし、むやみに刈るつもりはございません。あなたの守ってこられた方が、命の活かし方を誤り、取り返しのつかないほど道を踏み外さない限り、刈り取りは保留するつもりです。あなたの大切な存在を奪わずに済むよう、私も尽力いたします。どうか、ご理解ください。
他にも選択肢はある。だがなぜか、こうすることが自然に思えた。
突然、後頭部に何かが当たる。同時に、パシン、と乾いた音が響いた。
振り返ると、畳の上に丸めた雑誌が落ちていた。拾い上げる。輪ゴムで留められている。外すと、科学雑誌だった。
「どういうことですかね……?」
「理解はしたけど、調子に乗るなってところちゃうか」
苦笑気味に、彼は言った。
「挨拶代わりかもしれませんよ。全然痛くなかったですし」
彼と顔を見合わせる。
──あっ。
バゴン、と鈍い音が響く。
「うわっ!?」
今度は彼の後頭部だ。彼の後ろから、分厚い化学の専門書が飛んできた。
「待てや!何で俺までしばかれなあかんねん!しかも、めっちゃ痛いやんけ!」
「……活、ですかね。それか、守護霊心を解さない男に制裁、とか」
「やかましい。こいつ、絶対性格悪いわ」
彼は頭をさすりながら、苦笑いを浮かべた。つられて、こちらも緊張が解けていく。
「これは、一種の返事かもしれませんね」
「つきあう気はある、ってか?」
「ええ。なので、僭越ながら交渉成立、ということで」
彼が黙って頷く。また笑っている。
しばらくして、炊飯器から控えめな電子音が響いた。程なくして湯気がゆっくりと立ち昇り始める。それを、じっと見つめる。湯気の向こうの生活感が、少し遅れて胸に届く。言葉になる前の何かが、胸に迫る。それが何かは、わからない。言葉にもできない。ただ、確かに心のどこかが反応した。