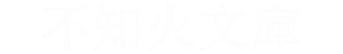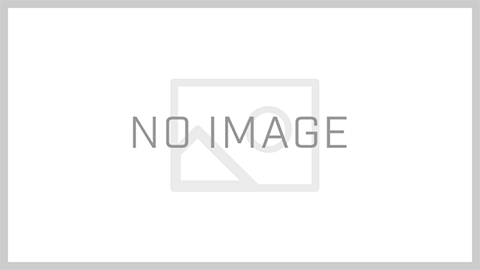【1】
朝食後、背筋にすうっと寒気が走った。今までに何度も感じたことがある、「あの」感覚だ。
──今日、か。思ったより早いな。
先の方から根元に向かって、手足がじりじり熱くなっていく。何度経験しても、これには慣れられそうにない。
彼は、出勤の支度を始めている。目立たないグレーのスーツに、白色のワイシャツ。ネクタイは淡いストライプ。誰が見ても、そこらにいる普通のサラリーマンだ。
その様子を横目に掃除をする。食器を流しに下げながら彼を一瞥する。特に変わった様子はない。
リビングの床には、ほんの少しの埃が落ちている。掃除機をかけていく。ソファの近くから順に、ソファの上にもかけていく。かばんがソファの上にある。
彼が洗面所に行く。かばんをそっと持ち上げる。念のため、ラックの上にあるぬいぐるみに目配せする。古びたクマのぬいぐるみ。
こちらを見ている気がした。無言で目配せを返した。
──仕事の邪魔、しないでくださいね。
心の中で呟き終えるや否や、後頭部に軽い衝撃。パーン、と乾いた音が頭上で地弾けた。
「痛っ!」
直後、床からすとん、と音がした。スリッパだった。
そのすぐ後、彼が洗面所から戻ってきて、こちらをじろりと睨んだ。
「さっき、なんか言ってへんかったか」
淡々と尋ねてくる。一応、警戒はしているのだろう。
「ええ、ソファの上を掃除しようとすると、スリッパが飛んできまして」
「お前、またろくでもないことしようとしたんやろ」
疑われるのも、日常だ。
「掃除機をかけるために、かばんを動かそうとしただけです」
「ふうん。そう簡単には認めへん、ってことなんちゃうか。しらんけど」
あっさりとそう言い放ち、彼はかばんを手に取った。玄関へ歩いていく。私は、掃除機のスイッチを切り、壁に立てかける。扉から顔をのぞかせて、彼に声を掛ける。
「いってらっしゃいませ、お館様」
この一言で振り返るかどうか、少しだけ賭けていた。
「今度はお館様か。まあええ、行ってくるわ」
彼は靴ひもを結びながら苦笑している。そういうところが、面白い。
──死神は、刈る相手に情を持ってはいけない。
そんな決まりが、あるわけではない。しかし、半ば不文律として存在する。当然といえば当然だ。情は仕事の妨げにしかならないのだから。
「ええ、お気をつけて。今日は布団を干したり、窓の掃除をしたりしておきますね」
「ああ、任せるわ。ありがとうな、助かるで」
扉が閉まる音がして、チェーンの外れた金具が軽く鳴った。彼の背を見送るとき、自然と口から声が漏れた。
「こちらこそ、どうも」
小さく呟いた直後、また脳天に軽い衝撃があった。今度もスリッパだった。だが、最近はいつも手心を加えてくれる。苦笑しながら心の中でひとこと漏らす。
──ご協力、どうも。
再度、掃除機を手にして、ソファを見る。座席のクッションの間に黒革の薄いフォルムがある。財布だ。ソファの前に屈んで手に取る。
「……さて、いきますか」
掃除を中断する。玄関へ向かう。ドアノブに手をかけて、気が付いた。
「あ、戸締り……」
──鍵を持っていない。
まずい、と思ったが、この家の玄関は扉が閉まれば自動的にロックがかかる。一度外に出てしまえば、ピッキングなどそう簡単にできる構造でもない。
「まあ、大丈夫か」
財布をローブの右内ポケットに突っ込んで、玄関に足を向ける。ぬいぐるみに、目をやる。何も飛んでこない。さっきまでの気配は、もうなかった(付喪神は摘葉の方についていっているから)
そのまま玄関を出る。エレベーターに乗る。一人、乗っていた。鏡に映る姿は一人だけだ。階数表示が減っていくのを待つ。扉が開く。乗り込み口に人が二人。わたしが通り過ぎても、視線はぶれない。
エントランスにもセキュリティはある。不審者はここでもある程度弾かれるだろう。
エントランスの自動扉が、静かに開く。外の空気は思っていたより湿っていた。
──うまくできる、だろうか。
握った手のひらが汗ばんでいる。何もしない方が、いいのだろう。その方が、おそらく万事うまくいくし平穏。十中八九、そうだろう。だが、言葉にするのはたやすいが、心にそれを納得させるのは、さほどたやすくない。
朝の光が、白くアスファルトに降り注ぐ。通勤ラッシュが終わったばかりだが、人々が多く行き交う道を、小走りで進み、彼の後を追った。
(いつもなら、この道中で困っている人間を一人二人、助ける。道端で転んだ老人とか、赤信号を渡ろうとする子供とか。そういう些細な介入が、死神としての「気まぐれ」のようなものだった。だが、今日は違う。誰かに手を差し伸べる余裕はない。私はただ急いで、彼の背中を追い続けた。)
途中、困っている人たちがいた。落とし物に気づかない老人。信号を渡り損ねた子供。自転車に轢かれそうになっていた犬。すべて間に合う距離にいる。でも、いつものようにはしない。先を急ぐ。
人々は私の存在には気付かない。死神は、標的以外の目には映らない。
──やはり皆、気が付かない、か。
便利な能力だが、時々思うことがないではない。まるで幽霊のように、存在すら認識されず街に紛れている。そのことを意識するほど、自身の存在というものに確証も自信も持てなくなる。
だが、今は感傷に浸っている場合ではない。
──時間はあまりない。急がないと。
外事課の仕事は、外回りが多いという。彼を見つけたのは、駅正面にあるビルの裏手だった。私は少し離れた場所に立ち、彼を見守る。何気なく建物の壁にもたれてスマートフォンを操作していた。ぱっと見はやはり普通のサラリーマンだ。しかし、彼の目は違っている。街を見ているようで、決して見ていない。常に周囲に気を配り、観察し、次の動きを想定している。
だからだろうか。すぐ彼に気づかれてしまった。彼と目が合う。私に気づいた。
「……」
軽く顎をしゃくり、彼は裏路地へ足を向ける。私はその背に従った。裏路地はひっそりと静まり返っていた。ゴミ袋の山と、割れたビール瓶の破片。都会の朝の裏側の顔。彼はそこで立ち止まり、私を振り返った。
「急に来るなや。何の用や」
落ち着いた声で、しかしやや警戒気味に。
「あなた、財布を忘れたでしょう。持ってきましたよ」
僕は内ポケットから、彼の財布を取り出す。革の質感は、朝よりも温かかった。
「財布……?」
彼は財布を受け取って、まじまじ見つめた。そして、中身を確認した。
「確かに俺のやつやな。おかしいな、かばんに入れたはずなんやけど」
その表情には、わずかに困惑が混じっていた。
財布を胸ポケットに滑り込ませ、そのまま裏路地の奥へ数歩移動する。通りから見えにくい位置。音だけが届く場所。仕事柄、こういう立ち位置を身体が覚えてしまったのだろう。わたしは、影の中に立った。
「というか、なんで場所が分かった」
問いかけられて、僕は一拍置いてから言う。
「死神は人間より勘が鋭いんです」
「ほう、初対面の標的にボコボコにされたことがあるやつでも?」
「あのときはやる気なしモードだったので」
「今は、違うんか」
「ええ、それはもう」
殺気を含んだように見せかけた笑顔を浮かべると、彼は肩をすくめた。
「へえ、そりゃ気をつけんとな」
「ぜひ、そうしてください。その方が刈り甲斐も出てくるというものです」
彼に向って笑いかける。しばらく言葉が途切れる。
「で、なんでここが分かったんや」
「……あれ? せっかくはぐらかせたと思ったのに。言わなきゃだめですか?」
「気にはなるな」
「地道な調査のたまものです。死神は基本的に身軽なので」
彼はしばらく沈黙した後、口を開く。
「確かに時々尾行してくるもんな、お前」
「ええ」
「プライバシーも何もあったもんやないな」
「死神の辞書にそのような言葉はございませんので」
「ストーカー界のナポレオンかよ」
「いいですね、モリアーティ教授みたいで」
「犯罪の分野、ニッチすぎやろ。お前、それでええんかいな」
にやりと笑って親指を立ててやった。
「いいんですよ。それに、プライバシーについてはあなたの仕事も大して変わらないでしょう」
そう言うと、やれやれ、とため息をついた。彼は財布をポケットに戻しながら、彼がふっと笑った。
「たしかにそうかもな。とりあえず、財布、サンキュな」
「どういたしまして。それと、身の危険にはくれぐれもお気をつけて。仲間といえども、いつも味方とは限らないので」
その言葉を口にした瞬間、自分でも声の色が変わったのを感じた。声は自然に低くなっていた。彼もそれに気づいたのだろう。彼は目を細めた(表情がわずかに固くなる)。
「それ、お前が言うか。しかも真顔で」
「ええ、あなたは私の獲物ですので」
「どうしたんや、急に」
「……あなたは仕事柄、身を危険に晒しやすい。努々気を付けてください。特に、仲間と思っている者に対しては」
ほんの数秒、ふたりの間に沈黙が流れる。彼は何も言わず、ただ小さく頷いた。
「ところで、お前家の鍵持ってへんやろ。今家はどうなってるんや」
「大丈夫です。その点は抜かりなしですから」
「……なら、まあええわ」
彼はそれだけ言って、また街へ歩き出した。私はその背中を見送りながら、ふと自分の胸に手を当てた。心臓はない。けれど、確かに何かが鼓動していた。
歩道の端で、彼はわずかに振り向き、何も言わずに顎だけを上げた。わたしは頷かず、目で返す。
いつもの彼なら、ここで一度、通りの小さなカフェに寄る。今日は、それをしない。視線がカフェのガラスに吸い寄せられた後、ほんの一瞬だけ、止まったが、そのまま通り過ぎる。
仲間といえども、いつも味方とは限らない。
──あれで、十分だったろうか。
路地を出て、別の角から彼の動線に戻る。もう後はない。次は、より慎重にならなければいけない。